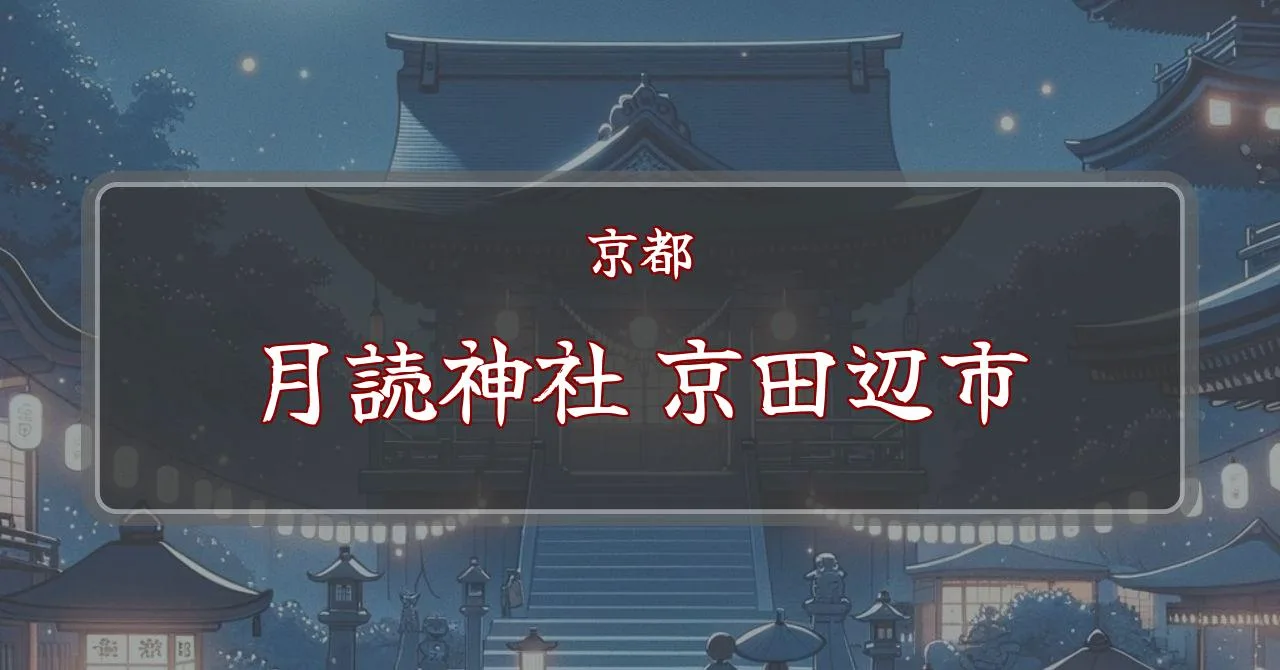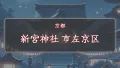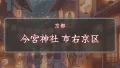京田辺の神秘!月読神社例祭「大住隼人舞」2025
イベントの概要
京都府京田辺市にある月読神社で、2025年10月中旬(※公式発表待ち)に開催される例祭、「大住隼人舞」は、京田辺市の無形民俗文化財に指定されている歴史深いイベントです。約1300年前、奈良時代に九州地方から移住してきた大住隼人が朝廷に奉納した舞が起源とされ、現在も地元の中学生たちが古代の衣装を身にまとい、太鼓や笛の音に合わせて力強く舞を奉納します。 舞いには、お祓いの舞、神招の舞、振剣の舞、盾伏の舞、弓の舞、松明の舞の6種類があり、小学生女子による隼人踊りも披露されます。 神聖な雰囲気の中、勇壮な舞と伝統音楽が織りなす、息を呑むようなパフォーマンスは必見です。 例祭当日は、屋台や縁日、盆踊りなども開催され、地域全体が活気に満ち溢れます。大住駅より徒歩10分とアクセスも良好です。古の伝統と現代の息吹が交差する、忘れられない体験をしてみませんか? 詳細な日程や時間は、公式発表をお待ちください。
基本情報
- 開催日: 2025年10月中旬(公式発表待ち)
- 開催時間: 18時30分~(2019年、2018年は18時30分開始。2025年は公式発表待ち)
- 住所・開催場所: 京都府京田辺市大住 月読神社
- 主催者・運営: 一般社団法人京田辺市観光協会
- 主催者・運営電話番号: 0774-68-2810
- 最寄り駅: JR学研都市線 大住駅(徒歩約15分)
主なイベント
月読神社例祭のハイライトは、京田辺市の無形民俗文化財に指定されている「大住隼人舞」です。約1300年の歴史を持つこの伝統芸能は、奈良時代に九州地方から移住してきた大住隼人が朝廷に奉納した舞が起源とされています。 現代では、地元の中学生たちが受け継ぎ、例祭の宵宮で奉納されます。 勇壮な舞と、太鼓や笛などの伝統音楽が織りなす神聖な雰囲気は、見る者を圧倒するほどの迫力です。 例祭当日は、大住隼人舞以外にも、地域住民による屋台や縁日、盆踊りなどが開催され、賑やかな雰囲気の中で、古の伝統と現代の活気が融合した、忘れられない一日を過ごすことができます。
大住隼人舞
大住隼人舞は、四隅に斎竹(いみたけ)を立て、注連縄を張った舞台で行われます。正面の大竹には天蓋が付けられ、5色の幡が垂れ下がり、米や塩、野菜などが供えられます。 舞人は地元の中学生たちが務め、古代の衣装を身につけ、手に剣や盾、扇、鈴などを持ち、太鼓や龍笛(りゅうてき)の音に合わせて舞います。 舞の内容は、お祓いの舞、神招の舞(かみおぎのまい)、振剣の舞(ふりつるぎのまい)、盾伏の舞(たてふせのまい)、弓の舞、松明の舞(たいまつのまい)の6種類があり、小学生女子による隼人踊りも披露されます。 それぞれの舞には、神話の物語や、隼人の歴史が込められており、見る者に深い感動を与えます。 その所作は、まるで「日本書紀」の海幸彦が溺れる様子を表現しているかのような力強さと繊細さを兼ね備えています。 伝統を守りながら、現代に受け継がれる大住隼人舞は、まさに京田辺の宝と言えるでしょう。
- 内容:地元の中学生による古代の衣装を身につけた伝統舞踊の奉納
- 特徴:太鼓や笛などの伝統音楽との共演、お祓いの舞、神招の舞、振剣の舞、盾伏の舞、弓の舞、松明の舞など複数の舞の構成、小学生女子による隼人踊り
- 歴史:約1300年前の奈良時代に起源を持つ、京田辺市の無形民俗文化財
屋台・縁日
大住隼人舞以外にも、例祭当日は多くの屋台や縁日が並びます。 地元の特産品や、子供たちが楽しめるゲームなど、様々な出店が立ち並び、活気に満ちた空間が広がります。 家族連れで楽しめるアトラクションも多く、一日中楽しむことができます。
- 内容:様々な屋台や縁日の出店
- 特徴:地元の特産品や子供向けゲームなど、多様な出店
盆踊り
夜には、盆踊りが開催されます。 地域住民が一体となって踊る盆踊りは、例祭の賑やかさをさらに盛り上げます。 参加者同士の交流を深める場としても、重要な役割を果たしています。
- 内容:地域住民参加型の盆踊り
- 特徴:地域住民の交流の場
アクセス方法
月読神社へのアクセスは、JR学研都市線「大住駅」から徒歩約15分です。 駅からは比較的平坦な道を進みますので、歩きやすい道となっています。 公共交通機関を利用される場合は、大住駅を目指してご来場ください。 お車でお越しの際は、近隣の駐車場をご利用いただくか、公共交通機関のご利用をお勧めします。
- JR学研都市線 大住駅より徒歩約15分
駐車場情報
月読神社に直接併設された駐車場はありません。近隣の有料駐車場をご利用ください。
- 近隣の有料駐車場をご利用ください。