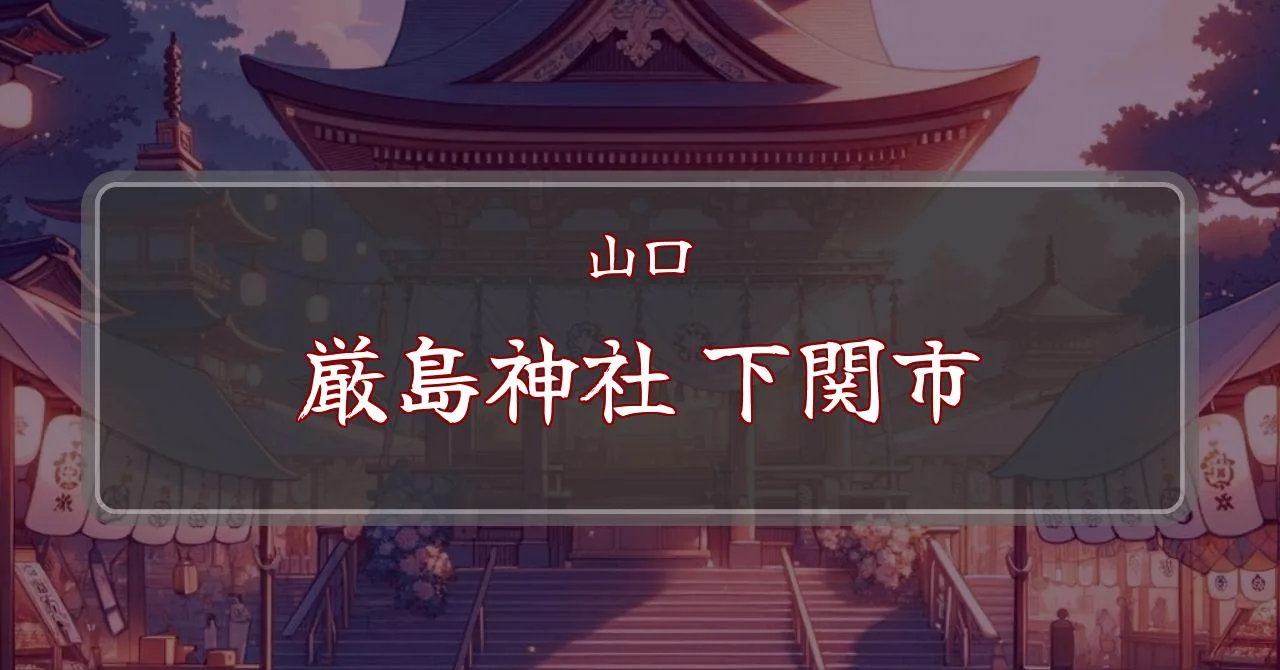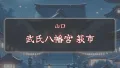下関の七年に一度の奇祭!令和7年浜出祭
イベントの概要
山口県下関市豊北町で、7年に一度、4月初旬に開催される「浜出祭」。約740年の歴史を持つこの祭りは、鎌倉時代の元寇で犠牲となった兵士の霊を鎮めるために行われたのが始まりと伝えられています。山側の田耕神社と海側の神功皇后神社の合同祭礼で、かつては田耕地区から土井ヶ浜まで約15kmの道のりを神輿を担いで歩く壮大な行列が繰り広げられていました。しかし、近年は人口減少などの影響を受け、行列はバス移動が中心となっています。
祭りのハイライトはなんといっても「鰤切(ぶりきり)」!10kgにも及ぶ大きなブリを、特別な作法で豪快にさばく様子は圧巻です。この鰤を食べることで7年間病気にならないという言い伝えも残っています。その他にも、奏者交換、浜殿祭など、古式ゆかしい神事が数多く行われ、歴史と伝統を感じさせる神聖な雰囲気に包まれます。近年は規模を縮小しての開催となっていますが、それでもなお、地域住民の強い思いと、古き良き伝統を守り続ける姿は、多くの感動を与えてくれます。令和7年(2025年)の浜出祭は、4月6日(日)に開催されました。桜が満開の美しい景色の中、簡略化されたとはいえ、晴天のもと盛大に行われ、多くの見物客を魅了しました。
神事の詳細は以下の通りです。
浜出祭 神事詳細
- 4月6日(日)
- 午前10時:田耕神社発輿祭:厳島神社の神輿の出発の儀式。時代衣装をまとった行列が境内を出発します。
- 午前10時~:田耕行列出立:田耕神社からバスで移動。青空のもと、多くの見物客に見送られながら出発します。
- 午後1時:奏者交換:土井ヶ浜の祭場で、田耕と神玉の使者が神官や関係者間を行き来し、口上を述べる儀式。かつては「堀切出合」と呼ばれ、堀切で行われていました。
- 午後1時~:土井ヶ浜祭場到着:神玉側の神功皇后神社の神輿と合流し、合同で神事が行われます。
- 午後3時:浜殿祭:土井ヶ浜祭場で、祓式、祝詞奏上、蟇目(ひきめ)、神子ノ舞、神酒三献、そしてメインイベントの「鰤切」が行われます。
- 午後3時~:鰤切(魚据・鰤切・披露):神玉側が用意した大きな鰤を、田耕側の「鰤切」役が豪快にさばく様子は圧巻です。
- 午後4時~:餅まき・直会:来賓挨拶、祝盃、主催者挨拶の後、餅まきが行われ、関係者で直会が行われます。
- 午後5時頃:神輿の帰還:両神社へ神輿が戻り、浜出祭が終了します。
七年に一度の貴重な機会、ぜひ下関の浜出祭を訪れて、歴史と伝統、そして地域の人々の熱意に触れてみてください。
基本情報
- 開催日: 2025年4月6日(日)
- 開催時間: 午前10時~午後5時頃(神事の進行により変動あり)
- 住所・開催場所等:
- 主な開催場所:下関市豊北町土井ヶ浜(土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム駐車場付近の祭場)
- 関連神社:
- 田耕神社(山口県下関市豊北町大字田耕)
- 神功皇后神社(山口県下関市豊北町大字神玉)
- その他:祭事の一部は田耕神社境内、神玉地区などでも行われます。行列はバス移動が中心です。
主なイベント
令和7年(2025年)の浜出祭は、規模を縮小しての開催となりましたが、7年に一度の伝統行事として、多くの神事が執り行われました。山側の田耕神社と海側の神功皇后神社から神輿が出発し、かつては15kmにも及ぶ行列が土井ヶ浜まで続いていましたが、今回はバス移動が中心となりました。それでも、神事の厳かさと、地域住民の熱意は変わらず、多くの見物客を魅了しました。
田耕神社発輿祭
午前10時、田耕神社では発輿祭が行われました。これは、田耕神社に合祀されている厳島神社の神輿の出発を祝う儀式です。境内には、時代衣装をまとった行列の参加者が集まり、神輿を中心とした行列が形成されます。本来は「将家太夫」「太刀将家」といった子役も多数参加しますが、今回は花神子と幣持役のみの参加となりました。行列は、幟がはためく境内から出発し、長い参道を下って三つの鳥居をくぐり、粟野川を渡ってバス乗り場へ向かいます。
奏者交換
午後1時からは、土井ヶ浜の弥生橋横の祭場で「奏者交換」の儀式が行われます。田耕と神玉、ふたつの陣屋(小屋)が向かい合って設けられ、双方の神官や花神子、伝御長、大年寄などが座ります。この儀式は、かつては神玉地区に入る「堀切」で行われ、「堀切出合」と呼ばれていました。「奏者」とは、双方を行き来する使者のことで、裃姿の使者が神官から神官へ、伝御長と大年寄の間を往復し、刀捌きを含む作法にのっとり、口上を述べます。行列が合流して土井ヶ浜へ向かうための申し合わせが、儀式として行われる点が興味深いものです。
浜殿祭
午後3時、土井ヶ浜祭場の神官座で「浜殿祭」が始まります。「殿」は、この場合、建物や座席を指します。浜出祭の別名としても使われますが、一連の祭礼のうち、土井ヶ浜に設けられた座で行われる行事だけを指すこともあります。祓式や祝詞奏上など、通常のお祭りと同じ神事が行われますが、注目は神田神主(神功皇后神社宮司)による「蟇目(ひきめ)」です。「鏑矢」という笛のような矢を南西と北西に射て、音を立てて邪気を払います。その他、座席を変更する「菰敷(こもしき)」、座を清める「奉幣(ほうへい)」、神玉と田耕の花神子が座の中をぐるりと一周する「神子ノ舞」、神玉側からの神酒の振る舞いである「神酒三献(みきさんこん)」など、様々な神事が行われます。「神酒三献」は、田耕の女神と神玉の男神の神様の結婚式を思わせる「三々九度」という考え方もあります。
鰤切
浜出祭のメインイベントである「鰤切」は、神玉側が用意した10kgにもなる大きな鰤を、三つの座でそれぞれ行われます。神玉側の「魚据(うおすえ)」役が、見物客に披露した後、田耕側の「鰤切」役の前に置かれます。田耕側は、こっそりと用意した大きな金箸と包丁にすり替え、魚には手を触れずに箸で鰤をつかみ上げ、「これ見たか!」と声をあげながら、まな板を包丁の背で三度打ちます。この豪快な様子は、大きな拍手喝采を浴びます。その後、三つ切りにされた鰤は、「垣内(かがち)」に運ばれ、酒粕で和えて御膳に盛られ、「膳据(ぜんすえ)」として、座の諸役に振る舞われます。かつては見物客にも振る舞われていましたが、衛生上の問題からか、今回はありませんでした。
餅まき
来賓挨拶と祝盃、主催者挨拶の後、山口県民の必須行事ともいえる餅まきが行われます。その後、両神社へ神輿がご帰還し、浜出祭は終了します。
- 内容:上記の各神事の他に、時代衣装をまとった行列、法螺貝の音色、太鼓や鐘の音など、五感を刺激する様々な要素が含まれています。
- 特色:7年に一度という希少性、古式ゆかしい神事、豪快な「鰤切」、地域住民の強い伝統へのこだわりなど、多くの見どころがあります。
アクセス方法
浜出祭の主な会場である土井ヶ浜祭場は、下関市豊北町土井ヶ浜にあります。公共交通機関を利用する場合は、JR山陰本線特牛駅が最寄りの駅となります。駅から祭場までは、タクシーまたはバスを利用するか、徒歩で約30分~1時間程度かかります。車でのアクセスも可能です。詳細は下記をご参照ください。
- 電車の場合:JR山陰本線特牛駅下車後、タクシーまたはバス、徒歩で会場へ。
- 車の場合:中国自動車道下関ICから国道191号線を経由して豊北町方面へ。会場周辺には案内看板があります。
駐車場情報
- 土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム駐車場:祭場周辺に駐車場がありますが、台数に限りがあります。混雑が予想されるため、公共交通機関の利用が推奨されます。
その他の情報
浜出祭は、屋外で長時間過ごすイベントです。天候に左右されるため、服装や持ち物には十分注意が必要です。また、神聖な儀式であることを踏まえ、服装や行動には配慮をお願いします。
- 服装:動きやすい服装がおすすめです。日差しが強い場合は帽子や日焼け止めクリームも用意しましょう。雨天の場合は、雨具が必要です。
- 持ち物:飲み物、タオル、日焼け止め、雨具(天候により)、カメラなど。
- 天候:当日の天候予報を確認し、適切な服装・持ち物をご準備ください。荒天の場合は、イベント内容が変更または中止になる可能性があります。