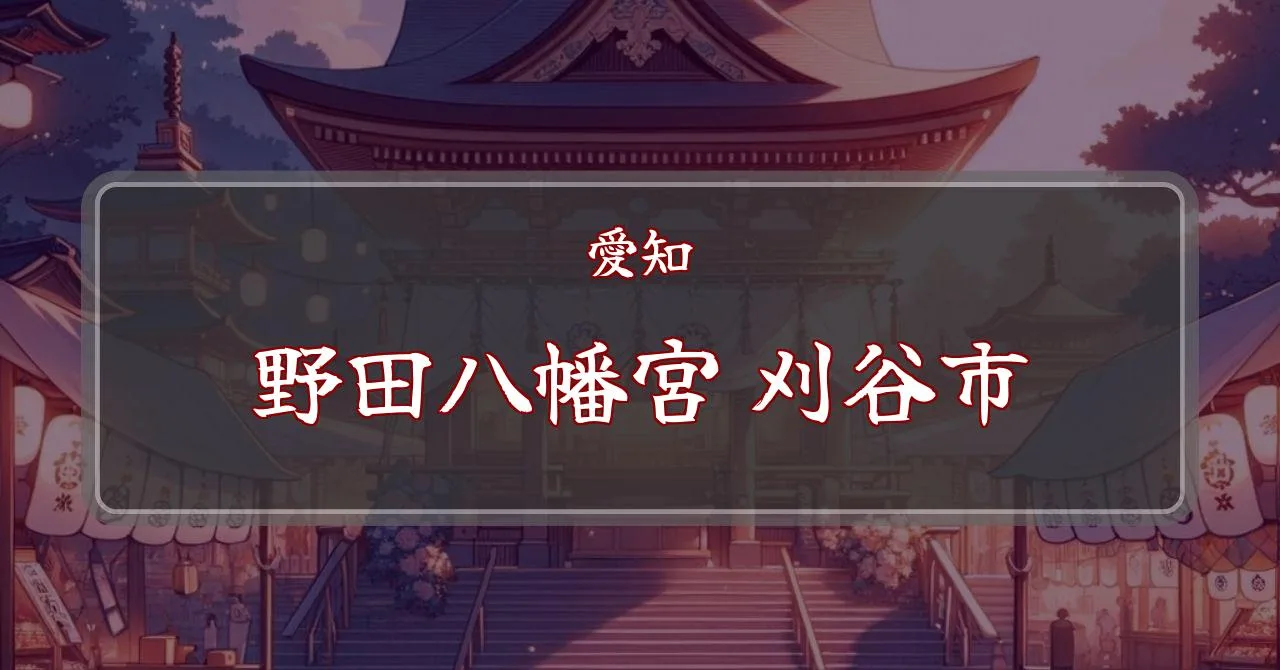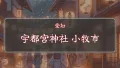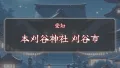2025年、刈谷の雨乞い!野田八幡宮例祭で歴史感じる旅
イベントの概要
愛知県刈谷市野田町にある野田八幡宮では、2025年8月24日(日)に、刈谷市無形民俗文化財に指定されている「野田雨乞笠おどり大会」が開催されます。 白鳳5年(676年)創建と伝えられる歴史ある野田八幡宮で、正徳2年(1712年)から続く雨乞いの儀式として受け継がれてきたこの伝統的なお祭りは、2人1組の踊り手が太鼓を中心に向かい合い、「つつろ」と呼ばれる短いバチを使って踊る独特の様式が特徴です。 踊り手は浴衣に赤い襷をかけ、紅白に彩られた菅笠をかぶり、桐の木で作った「つつろ」を手に、雨乞いの唄と囃子に合わせて力強く踊ります。大きく笠を振る姿は圧巻です。「場ならし」「三拍子」「ささら」「綾」「おさめ」という順番で繰り広げられる踊りは、農民の雨への切実な願いが感じられる、素朴で趣のあるものです。 昭和17年(1942年)に一度途絶えましたが、昭和54年(1979年)に地元の熱意によって復活。以来、野田雨乞笠おどり保存会によって大切に継承されています。 2025年の例祭では、古文書にも記録が残る歴史深い踊りを間近でご覧いただけます。 かつての雨乞いの儀式が現代に息づく、貴重な文化体験となるでしょう。 ぜひ、歴史と伝統を感じながら、忘れかけていた日本の原風景に触れてみてください。
基本情報
- 開催日: 2025年8月24日(日)
- 開催時間: 16:00~
- 開催場所: 野田八幡宮境内
- 住所: 〒448-0803 愛知県刈谷市野田町東屋敷62
- お問い合わせ: 080-6192-9274 (野田雨乞笠おどり保存会) info@nodaamagoi.sub.jp
- 駐車場: 無し
- 料金: 無料
主なイベント
野田雨乞笠おどり大会のメインイベントは、正徳2年(1712年)から続く伝統的な雨乞い踊りの奉納です。 この踊りは、かつて農民たちが豊作を祈願するために奉納していたもので、現在もその伝統が受け継がれています。 2人1組の踊り手が、太鼓を中心に向かい合って踊る様は、息の合った動きと力強いリズムが特徴です。 紅白の菅笠と赤い襷、そして桐の木で作った「つつろ」という短いバチを使った独特の踊りは、見る者を魅了します。 雨乞いの唄と囃子に合わせて踊られる様は、古き良き日本の伝統文化を感じさせる、大変貴重なものです。
野田雨乞笠おどり
野田雨乞笠おどりは、単なる踊りではなく、豊作を祈願する神事としての側面も持ち合わせています。 踊り手たちは、真剣な表情で、太鼓の様々な面を「つつろ」で打ち鳴らし、独特のリズムを生み出します。 踊りの種類は複数あり、「場ならし」「三拍子」「ささら」「綾」「おさめ」という順番で演じられます。それぞれの踊りには見せ場があり、大きく笠を振る姿は、雨乞いへの強い願いを象徴しているかのようです。 素朴ながらも力強い踊りは、観る者に感動を与え、日本の伝統文化の深さを改めて感じさせてくれます。 この機会に、歴史と伝統が息づく貴重な踊りをぜひご堪能ください。
- 内容: 2人1組の踊り手が太鼓を中心に向かい合い、「つつろ」という短いバチを使って踊る雨乞い踊り。
- 特徴: 浴衣に赤い襷、紅白の菅笠、桐製の「つつろ」を使用。力強いリズムと大きく笠を振る姿が特徴。
- 構成: 「場ならし」「三拍子」「ささら」「綾」「おさめ」の順に踊りが展開される。
- 歴史: 正徳2年(1712年)から続く、刈谷市無形民俗文化財に指定された伝統芸能。
価格・チケット情報
野田雨乞笠おどり大会は無料でご観覧いただけます。
アクセス方法
野田八幡宮へのアクセス方法は以下の通りです。
- 電車:JR東海道本線(浜松~岐阜)「野田新町駅」下車後、徒歩約15分。
駐車場情報
野田八幡宮には駐車場がありません。公共交通機関をご利用いただくか、近隣の有料駐車場をご利用ください。
その他の情報
野田雨乞笠おどりは、屋外で開催されます。天候に左右される可能性がありますので、当日の天候予報を確認の上、服装・持ち物をご準備ください。熱中症対策として、水分補給をこまめに行うことをお勧めします。また、歩きやすい靴を履いてご来場ください。